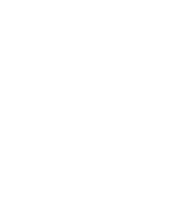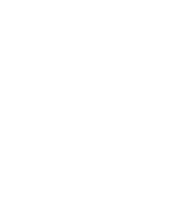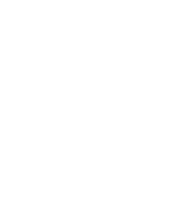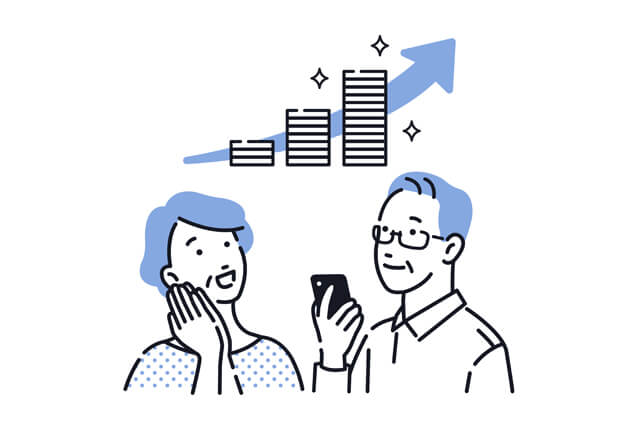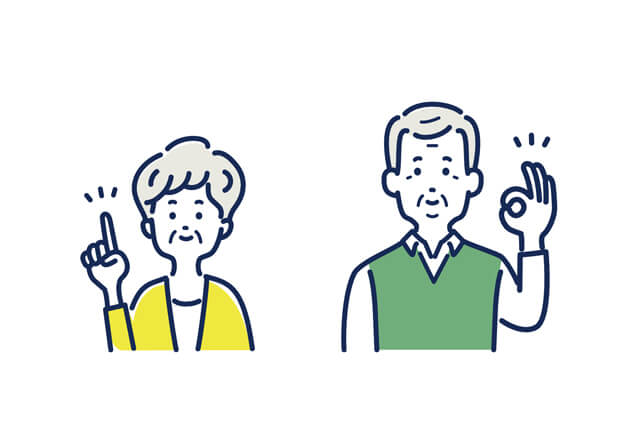私たちがお一人おひとりのために考えます
「60歳からの住み替え資金」相談するならSBIシニアの住まいとお金
お客さまから選ばれる3つの理由
1
信頼と安心の
SBIグループ
2
住宅ローンの
プロがサポート
3
相談料等は
すべて無料

銀行でもない、不動産会社でもない、SBIシニアの住まいとお金なら解決できることがあります。
【住み替え資金相談】は
このような方にご利用いただいております。
- 予算に見合った物件が見つからない方
- 年齢と資金不足を理由に住み替えを断念された方
- 今の持ち家が想定金額で売却できるか不安な方
- なるべく手元に資金を残したいと思っている方
- 無理のない資金計画で住み替えを行いたい方
住宅ローンのプロが
お一人おひとりに寄り添った
アドバイスを致します。
【住み替え資金相談】で
できること
購入も売却も適正価格
ご自宅の売却価格や
新居の購入価格も適正な価格で
相談ができます
豊富なシニア向け商品でご検討
リ・バース60やリースバックなど
シニア向けの商品やサービスの
相談ができます
無理のない資金計画で老後も安心
住み替え予算から
住み替え後の返済計画まで
相談ができます
SBIシニアの住まいとお金は東証プライム上場SBIホールディングス
のグループ企業が運営しています。
SBIシニアの住まいとお金の
相談サービスが
選ばれる3つの理由

信頼と安心のSBIグループ

住宅ローンのプロが丁寧にサポート

ご相談は何度でも無料
お客さまお一人おひとりにあったアドバイスをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
【住み替え資金相談】ご利用の流れ
お問い合わせ
Webフォームよりお気軽にお問い合わせください。
電話相談
専門の相談スタッフよりご連絡差し上げます。住み替え先の物件情報やお客さまの状況をお伺い、お客さまの悩みや疑問に対して、アドバイスをさせていただきます。
代表的なヒアリング項目は下記のとおりです。
◆購入物件情報
購入価格、築年数、所有使途、売買契約の有無、不動産会社への相談状況
◆お客さまのご状況
年収、住宅ローンの借り入れ状況、その他借り入れ状況、ご自宅の状況、ご用意される自己資金額
ご提案・ご紹介
電話相談の結果を受け、資金計画の作成を行います。物件購入時の資金計画と返済プランはもちろんのこと、予算に見合った物件や、シニア向けの各種商品を活用した無理のない資金計画をご提案させていただきます。その後、資金計画で提案させていただいた商品の提供会社や提携不動産会社をご紹介いたします。
【住み替え資金相談】よくあるご質問
相談料や手数料はかかりますか?
相談や資金計画のご提案、提携先のご紹介まで、手数料は一切かかりません。
予算に見合う物件が見つからないのですが、相談できますか?
ご予算をお決めになる段階でぜひご相談ください。お客さまの状況を詳しくヒアリングさせていただいた後に、多様な商品やサービスから最適なものを選択し、ご予算に関するご提案(※)をさせていただきます。ご予算の確定後に、ご希望に沿った物件をご紹介させていただきます。※紹介及び相談に関して費用は一切かかりません。ご予算を無理に上げる提案も致しません。
自宅(現住居)の売却に関しても、相談できますか?
ご自宅の売却に関してもアドバイスさせていただきます。資金計画をご提案する中で、ご自宅の想定売却価格を把握できます。
相談時間はどのくらいですか?
電話相談の際は、30分程度のお時間でアドバイスさせていただきます。
すでに他社に問い合わせていますが、セカンドオピニオンとしての相談は可能ですか?
はい、当社ではセカンドオピニオンも受け付けております。もし既に他社に申し込みをした後でも、ご不安な方はお気軽にお問い合わせください。お客さまの状況を丁寧にヒアリングしアドバイスさせていただきます。
対面での相談もできますか?
電話相談の後、資金計画のご提案や提携先のご紹介の際に、店舗やご自宅での相談も可能です。詳しくは相談スタッフにお尋ねください。
お役立ち情報
住まいとお金に関するお役立ち情報を発信しています。
ゆとりある暮らしの実現に向けて、ぜひお役立てください。
コラム

人生の終盤をどう過ごすか、それは誰にとっても避けられないテーマです。近年では「終活」という言葉が広く知られるようになり、将来に備えて準備を始める人が増えています。とはいえ、「何から始めればいいか」「いつ始めるのがいいのか」と悩む人も多いのではないでしょうか。 この記事では、終活を始めるタイミングや進め方、準備すべきことについて、具体的なステップを解説します。
終活はいつから始めるべき?年代別の進め方
株式会社NEXERが行った調査によると、終活を始めるのにふさわしい年代として、「60代頃」と回答した人が31.2%、「70代頃」と回答した人が36.9%、「80代頃」と回答した人は10.3%でした。つまり、60代~70代が全体の約7割を占めています。
出典)株式会社NEXER、森正株式会社(SAIKAI&CO.)「【終活、何をする?】実際に終活を行っている78.7%が「不用品処分をしている」」
終活を始めるのにふさわしい年代として、60代~70代と答える人が多い一方で、早く始めると安心できる要素も多分にあるでしょう。あくまで目安ですが、年代別に以下のようなイメージで進めるといいでしょう。 50代:終活の情報収集とライフプランの見直し
将来に備えた準備期間として、情報を整理し始める時期です。まだ終活には早いと感じる方も多いですが、50代は「準備期間」として最適です。老後の生活設計や医療・介護の希望、資産の棚卸しなど、情報を整理し始めることで、60代以降の終活がスムーズになります。 ライフプランを見直す
エンディングノートを下書きする
相続や保険を見直す 60代:終活を本格的に始める
生活が安定し始めるこの時期に、終活の基盤を整えましょう。多くの人が終活を始める年代であり、家族との話し合いや書類の整理を進めるのに適しています。 遺言書を作成する
医療や介護についての希望を伝える
不用品の整理や身辺整理をする 70代:終活の実行と確認
家族と共有する段階で、これまでの終活の準備を実際に形にしていく時期です。エンディングノートの完成や、家族への情報共有を行い、必要に応じて専門家のサポートを受けましょう。 エンディングノートを完成させる
家族へ情報を伝える
公正証書遺言を作成する 80代以降:終活の見直しと最終確認
終活の内容を定期的に見直し、家族と連携して安心を確保しましょう。体力的な負担を減らすためにも、家族や支援者と連携して進めることが大切です。 書類を再確認する
デジタル遺品を整理する
家族と定期的に話し合う時間を持つ 終活の進め方
終活は、人生の最終章を安心して迎えるための準備です。以下のステップに沿って進めることで、無理なく取り組むことができます。 ステップ1:目的を決める
まずは、終活を行う目的を明確にしましょう。代表的な例としては、以下のようなものがあります。 家族に迷惑をかけたくない
自分らしい最後を迎えたい
財産を整理したい
医療や介護の希望を伝えておきたい 目的がはっきりすると、何を準備すべきか見えてきます。
ステップ2:情報を整理する
次に、資産の内容や医療・介護に関する希望など、自身に関わることをリスト化しましょう。代表的な例としては、以下のようなものがあります。 資産(預貯金、不動産、保険など)
医療・介護に関する希望(延命治療の有無、施設の希望など)
家族や親族の連絡先
契約しているサービス(携帯、サブスクリプション、クレジットカードなど) 情報を整理することで、万が一の時にも家族がスムーズに対応することができます。 ステップ3:具体的な行動に移す
情報を整理したら、必要な手続きを進めましょう。 家族と話し合う
専門家へ相談する
遺言書・エンディングノートを作成する 特にエンディングノートは、自分の思いや希望を記録するのに適しており、終活を進めるうえで作成しておくといいでしょう。 終活の準備でやるべきこと
終活をスムーズに進めるためには、以下の分野での準備が重要です。 遺言書の作成
相続トラブルを防ぐうえで、遺言書を作成することは重要です。遺言書には法的効力があり、財産の分配方法や遺族へのメッセージを明確に残すことができます。 医療・介護の意思表示
将来、医療や介護が必要になったときに備えて、治療・介護の意思表示は事前に行いましょう。たとえば、延命治療を希望するかどうか、どのような介護施設を希望するかなどを明確にすることで、家族が判断に迷うことを防げます。 また、「事前指示書(リビング・ウイル)」や「尊厳死宣言公正証書」などの書類を活用することで、医療機関や介護施設に自分の意思を伝えることができます。
出典)公益財団法人 日本尊厳死協会「リビング・ウィルとは」
日本公証人連合会「尊厳死宣言公正証書」 資産の整理
相続の対象となる財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。そのため、正確な把握が必要です。 プラスの財産
マイナスの財産 現金
預貯金
株式等の有価証券
動産(車・貴金属・骨董品など)
不動産(土地・建物・駐車場など)
貸借権
特許権
著作権などの権利 など 借入金(ローン)などの債務
未払税金
未払費用
クレジットカードの利用残高 など 特に不動産や有価証券などは、評価額や名義の確認も必要になるため、早めに準備することが重要です。 身辺整理のコツと注意点
終活を進めるうえで、身の回りの整理は欠かせません。以下のポイントを押さえることで、家族の負担を減らすことができます。 モノの整理
思い出の品や長年使っていないものなどは、自分自身で整理するのが理想です。残すもの、譲るもの、処分するものの基準をあらかじめ決めると、作業がスムーズに進みます。
特に、写真や手紙などの思い出の品を残す場合は、家族にとっても大切なものになる可能性があるため、残す理由や背景をメモすると良いでしょう。 デジタル遺品
スマートフォンやパソコンなどのデジタル情報も忘れずに整理しましょう。これらの機器には、ネット上の資産を管理するアプリや、保険などの契約内容の確認メール等が集約されています。遺族がスマートフォンやパソコンのパスワードを知らない場合、ロックを解除することは非常に困難になり、デジタル遺品の確認を進めることも難しくなります。 信頼できる方法でパスワードやアカウント情報を記録・保管することが、家族の負担を減らす鍵となります。最近では、デジタル遺品専用の管理サービスやアプリも登場しており、活用することで安全かつ効率的に管理できます。
出典)独立行政法人 国民生活センター「今から考えておきたい「デジタル終活」 -スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために-」
家族に伝える情報
終活で整理した情報は、家族にしっかり伝えることが重要です。重要な情報(前述した内容や処分してほしいデジタル遺品や家族へのメッセージなど)は、エンディングノートにまとめましょう。エンディングノートを活用すれば、医療・介護の希望、財産の概要、連絡先、メッセージなどを一冊にまとめることができます。 ただし、エンディングノートには法的効力がないため、財産分与などの重要事項は遺言書と併用することが望ましいです。
出典)法務省「エンディングノート」
まとめ
本記事では、終活を始めるタイミングや終活の進め方や準備すべきことを解説しました。終活は、人生の終わりを意識することで、今をより大切に生きるための活動です。
また、終活を早めに準備することで、自身の心の余裕と家族の安心につながります。まずはエンディングノートの1ページを書いてみることから始めてみましょう。小さな一歩が、安心につながります。

人生100年時代、定年後の働き方として“起業”が注目されています。経験や人脈を活かせるメリットがある一方で、資金や健康面などの課題もあります。この記事では、60代から起業する魅力や注意点、資金調達の方法について詳しく解説します。
50~60代の起業への関心が増加中!シニアが選ぶ第二のキャリアとは
定年後に新たな挑戦として“起業”に関心を持つ50~60代が増えています。長年の経験や人脈を活かし、「自分らしい働き方」を求めて起業に踏み出すシニア層が注目されています。
実際、フリー株式会社が行った調査によると、50歳〜69歳の約4人に1人が起業に関心を持っています。さらに、そのうち約3割が『3年以内に起業を実現したい』と回答しており、起業への意欲の高さがうかがえます。この結果は、定年後の働き方として“起業”が現実的な選択肢になってきていることを示しています。
出典)フリー株式会社「起業に関するアンケート調査」
60代で起業するメリットとは?
60代で起業することには、他の年代にはない強みがあります。ここでは、シニアの起業における代表的なメリットをご紹介します。
豊富な経験と専門知識を活かせる
長年の職業経験で培ったスキルや業界知識は、起業後の事業運営において大きな武器になります。さらに、築いてきた人脈や信頼関係は、ビジネスの立ち上げをスムーズに進めるうえで大きな支えとなります。
時間的余裕と働き方の自由がある
定年後はフルタイム勤務に縛られることなく、自分のペースで働けるのが大きな魅力です。趣味やライフスタイルに合わせた働き方を選べるため、心身の負担を抑えながら、充実した起業ライフを送ることができます。
新しい学びや刺激が得られる
起業は常に新しい課題や学びに直面するため、脳の活性化にもつながります。ITやマーケティングなど、これまで触れてこなかった分野に挑戦することで、自己成長を実感できるでしょう。 60代で起業する際の注意点
豊富な経験や人脈を活かせる60代の起業には多くの魅力がありますが、成功のためにはいくつかの注意点も押さえておく必要があります。
体力・健康面のリスクがある
自分のペースで働けても、起業には長時間労働やストレスが伴うこともあります。若い頃に比べて体力が低下しているシニア層にとっては、身体的な負担が大きくなることがあります。無理のない働き方と、日々の健康管理が重要です。
事業が失敗するリスクがある
起業しても必ず成功するわけではありません。収入が安定するまで時間がかかることもあり、働ける年数が限られている60代にとっては、失敗のリスクを取り戻すのが難しい場合もあります。多額の資金を一度に投入するのではなく、小さく始めて徐々に拡大するなど、慎重な事業計画が欠かせません。
自己資金の準備と融資の難しさがある
年齢を理由に、金融機関からの融資が受けにくいケースもあります。そのため、自己資金の範囲で事業を始めることを前提に、現実的な資金計画を立てることが重要です。公的支援制度や助成金の活用も視野に入れましょう。 60代で起業する際の資金調達方法
起業には初期費用や運転資金など多くの資金が必要です。自己資金が足りない場合は、公的融資や助成金の活用が有効です。 公的融資制度
公的機関が提供している融資には、以下のようなものがあります。
新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫) 対象
新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方 融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円) 資金使途
運転資金・設備資金 出典)日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」 都創業融資(東京信用保証協会) 対象
次のいずれかに該当する方。 現在、事業を営んでいない方で、1か月以内に新たに個人で、または2か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画をお持ちの方
創業した日から5年未満の中小企業者、組合
分社化をしようとする会社または分社化により設立された日から5年未満の会社 融資限度額
3,500万円 資金使途
運転資金・設備資金 出典)東京信用保証協会「都創業融資(略称:創業)」 地方自治体の起業支援制度(東京都)
東京都は、都内の開業率のアップを目的として、創業助成金の制度を提供しています。 対象
都内での創業を具体的に計画している個人、または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 助成限度額
400万円 助成対象経費
事業費、人件費、委託費 出典)東京都「創業助成事業」 その他の資金調達
その他にも、以下のような資金調達方法があります。
家族や親戚からの借り入れ
開業資金を調達できない場合は、家族や親戚から借りるのも一つの方法です。ただし、親族からの借り入れは贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があるので注意しましょう。
クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の人々から少額ずつ資金調達する方法です。新規開業で実績がなくても、資金の使い道をアピールしたり、支援者への特典を用意したりすることで、開業資金を集められる可能性があります。
ビジネスローン(不動産担保ローン)
ビジネスローンは、主にノンバンクが取り扱っている事業者向けのローンです。無担保・無保証で利用できるローンもある一方で、公的な融資に比べると金利は高い傾向にあります。
また、自宅などの不動産を所有している場合は、不動産担保ローンも選択肢となります。不動産担保ローンは、無担保ローンに比べてまとまったお金を低金利で借りることができます。
関連記事はこちら開業資金はいくら必要?実績がなくても資金調達できる7つの方法
まとめ
本記事では、60代で起業するメリットや資金調達方法、注意点について解説しました。定年後の人生をどう過ごすかは、人それぞれです。起業という選択肢は、これまでの経験や人脈を活かしながら、自分らしい働き方を実現できる可能性を秘めている一方で、体力や資金、家族との関係など、慎重に考えるべき点も少なくありません。 大切なのは、「起業=正解」ではなく、「自分にとって納得のいく選択かどうか」を見極めることです。まずは、起業に関する制度や支援情報をチェックし、自分に合ったスタートの形を見つけましょう。

定年後に住宅ローンの返済が厳しくなったとき、どうすればよいか悩んでしまうでしょう。特に定年後は収入減や予期しない支出の増加などが起きやすく、住宅ローンの返済が苦しくなる傾向があります。そのため、返済が難しくなる前に返済計画を立てるなどの準備が大切です。本記事では、住宅ローンが払えなくなる原因と防ぐために実行すべき対処方法を紹介します。
定年後に住宅ローンが払えなくなってしまう理由
定年後に住宅ローンが払えなくなる主な原因は以下の理由です。 収入の減少
予期しない支出の増加 特に定年後は収入が大きく落ちるので注意
定年退職後は、現役時代と比べて収入が減少する傾向があります。収入源が年金となるため、現役時代と同じペースで住宅ローンを返済するのは難しくなるかもしれません。 出典)パーソル総合研究所|シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査 パーソル総合研究所の調査によれば、再雇用者の年収は平均で約44.3%減少しています。さらに、再雇用者の約5割は年収が半分以下になっていることが明らかになっています。 定年後の収入が大幅に減少する一方で、医療費や介護費用、住宅の修繕費など、老後特有の支出は増えていきます。
予期しない支出の増加が家計を圧迫する
医療費や介護費用、自宅の修繕費など、予期しない出費が発生すると住宅ローンの返済が難しくなる場合があります。高齢になると病気やけがのリスクが高まり、医療費や介護費用の負担が増えやすいです。予期しない支出として以下のような費用が挙げられます。 医療費
介護費用
自宅の修繕費
冠婚葬祭費用
保険料の支払い さらに、自宅の修繕やリフォームにかかる費用も予想外の支出として家計を圧迫します。支出が増え続けると、家計の余裕がなくなり、住宅ローンの返済にも影響が出てきます。
返済困難にならないための対処方法
住宅ローンは返済期間が長く、家計への影響も大きいため、将来のリスクに備えた早めの準備が大切です。収入が減った場合や予期しない出費が発生した場合でも、適切な対策を講じることで返済の負担を抑えられる可能性があります。 ここからは、住宅ローンの返済が難しくなる前に取り組める対策を紹介します。
専門家に相談して収益シミュレーションを作る
住宅ローンの返済が困難になるのを防ぐためには、専門家に相談して収益シミュレーションを作成しましょう。専門家の助言を受けることで、将来の収入や支出を具体的に予測し、無理のない返済計画を立てられます。 多くの金融機関や専門サイトでは、住宅ローンのシミュレーションツールを提供しています。住宅金融支援機構の「住宅ローンシミュレーション」では、借入金額や返済期間、金利などを入力することで、毎月の返済額や総返済額を簡単に試算できます。
ツールを活用し、早めに返済計画を見直すことで、将来の返済リスクを抑えましょう。
金融機関に相談する
住宅ローンの返済が厳しくなりそうな場合は、早めに金融機関へ相談しましょう。収入の減少や予期しない出費があっても、金融機関に相談すれば返済条件の見直しや柔軟な対応を受けられる可能性があります。 たとえば、フラット35には返済負担を一時的に軽減する返済特例制度(返済方法変更メニュー)があります。この制度は、病気や収入の減少などで返済が難しくなった場合に、一時的に返済額を減額できる制度です。 こうした制度を利用すれば、返済の負担を軽くできるかもしれません。金融機関への相談は早ければ早いほど選択肢が広がります。 支払いが滞る前に、返済期間の延長や一部繰り上げ返済の見直しなど、負担を軽減する方法を一緒に検討してもらいましょう。
住宅ローンの借り換えを検討する
住宅ローンの返済負担を軽減するためには、金利の低いローンへの借り換えも検討してみましょう。借り換えによって金利が下がれば、毎月の返済額や総返済額が減少します。 金利の低いローンに借り換えすることにより、家計の負担が軽くなり、将来の返済リスクも抑えられるでしょう。 ただし、借り換えには手数料や保証料などの諸費用がかかります。手続きも複雑なため、事前に総費用と効果をしっかり比較・検討しましょう。
返済が困難な場合はリースバックを検討する
万が一住宅ローンの返済が厳しくなってしまった場合は、家を売却して資金を確保するリースバックという方法があります。 リースバックは、自宅を売却した後、賃貸借契約を結び、そのまま住み続ける仕組みです。 売却で得た資金は住宅ローンの残債の返済や生活資金の確保に充てられ、経済的な負担を軽減しつつ、住み慣れた家での生活を維持できます。 リースバックの特徴
内容 売却後も居住継続
自宅を売却しても、賃貸借契約を結ぶことでそのまま住み続けられる。 売却価格
通常の売却よりも売却価格が低くなる傾向がある。 資金確保
自宅を売却することで、まとまった資金を確保できる。 固定費の安定化
固定資産税や修繕費などの負担がなくなり、家計管理がしやすくなる。 リースバックは、住宅ローンの返済に悩んでいる方や資金が必要な方にとって、住み慣れた家に住み続けながら資金を確保できる有効な方法です。ただし、家賃の設定や契約内容の確認が不可欠であり、再購入の可否や賃貸条件の変更などにも注意が必要です。
住宅ローンのよくある質問
ここからは、住宅ローンの返済や借り換えに関するよくある疑問について解説します。
住宅ローンが払えないと強制退去させられるの?
住宅ローンの返済が長期間滞ると、強制退去となる場合があります。返済が遅れると、まず金融機関から督促状や催告書が届きます。 それでも返済が行われない場合、金融機関は通常、競売の申立てを行います。競売が成立すると、所有者は強制的に退去しなければなりません。返済が厳しくなったと感じたら、早めに金融機関や法律の専門家に相談しましょう。
団信などは適用されないの?
団信(団体信用生命保険)は、住宅ローン契約者が亡くなったり、高度障害状態になった場合に、ローン残高を全額返済する保障を提供します。 団信の主な保障内容は以下のとおりです。 契約者が亡くなった場合
所定の高度障害状態に該当した場合 「住宅ローンが返済困難になった際に団信は利用できないか?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、上記のように、収入減少や失業、生活困窮などの場合には団信は適用されません。
住宅ローンは最長何歳まで借り換えできますか?
多くの金融機関では、住宅ローンの申込年齢を65歳以下か70歳未満に設定しています。そのため、70歳を超えると住宅ローンの借り換えは難しくなってくるでしょう。 ただし、一部の金融機関では「リ・バース60」という商品を提供しているため、70歳以上の方でも住宅ローンの借り換えをすることができます。リ・バース60は、原則満60歳以上の方を対象としたシニア向けの住宅ローンの一種です。毎月の返済は利息のみで、月々の返済負担を抑えられるメリットがあります。
まとめ
本記事では、住宅ローンの返済に関するリスクとその解決策について説明しました。収入の減少や予期しない支出の増加が原因で返済が困難になることはあります。そのような事態を避けるためには、早めに収益シミュレーションを作成し、金融機関に相談することで、返済負担を軽減できる可能性があります。返済が厳しくなったと感じた場合は、早めに行動し、適切な対策をとりましょう。
動画で学ぶ
この動画はこのようなお悩みをお持ちの方におすすめです
・住宅ローンの支払いが厳しくなった方
・銀行に住宅ローンの借り換えは難しいと言われた方 概要
SBIシニアの住まいとお金の住宅ローン相談に寄せられた実際のご相談を紹介します。今回の相談者は62歳の男性で、自身で会社経営をしています。現在は62歳でまだまだ仕事は続けていくつもりですが、直近のコロナ禍の影響で赤字決算になってしまい、毎月の住宅ローンの支払いが厳しくなりご相談いただきました。 ご相談者様の状況
・68歳男性 妻と子ども2名と同居
・事業収入(会社経営)
・住宅ローン残高 4,400万円
・住宅ローンの毎月の支払額 35万円 ご相談者のお悩み
・毎月の支払額を減らすために住宅ローンの借り換えをしたい
・条件が良い(金利が低いなど)金融機関を教えてほしい アドバイス
他の金融機関の金利が低い住宅ローンへ借り換え
まずは、他の金融機関の金利が低い住宅ローンへの借り換えを提案しました。当時の借り入れ時よりも、現在の金利水準が低く、借り換えメリットが十分に生まれたためです。しかしながら、ご自身が経営する会社が赤字決算であったため、銀行に相談するも審査が難しく断念されました。 リ・バース60への借り換え
リバースモーゲージ型住宅ローン「リ・バース60」は毎月の支払が利息のみになるため、近年では住宅ローンの支払いを減らす手段として注目されています。相談者様の場合は、住宅ローン残高が4,400万円であったため、仮に3%の金利で試算すると、毎月の支払が約11万円になり、約20万円の支払いの軽減が可能でしたが、法定相続人(お子様)の同意が得られなかったため、断念されました。 解決に向けた提案
本動画では、解決に向けた提案として、完済年齢を伸ばすことで住宅ローンの支払額を減らす方法について紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。 SBIシニアの住まいとお金に相談
SBIシニアの住まいとお金では、住宅ローンのお悩みを住宅ローンのプロに直接相談できます。相談料等は全て無料です。セミナーや相談事例に関する質問や相談も受け付けています。ぜひお気軽にご相談ください。 60歳からの住宅ローン相談はこちら
この動画はこのようなお悩みをお持ちの方におすすめです
・リースバックの家賃が払えなくなった方
・リースバックの利用後、買戻しを検討している方 概要
SBIシニアの住まいとお金のリースバック相談に寄せられた実際のご相談を紹介します。今回の相談者は68歳の男性です。リースバックは、売却時にまとまった現金を得られますが、その後は家賃の支払いが続きます。相談者様は、老後資金を確保するために数年前にリースバックの契約をしましたが、想定外の出費が重なり、毎月の家賃が払えなくなってしまったとのことでした。 ご相談者様の状況
・68歳男性
・年金収入のみ
・毎月の家賃 12万円 ご相談者のお悩み
・毎月の支払額を4万円減らしたい アドバイス
リースバック会社に家賃の値下げ交渉
まずは、リースバック会社に家賃の値下げ交渉をすることを提案しました。しかしながら、相談者様は断られる可能性が高いため交渉したくない意向があり、断念されました。 家賃の負担を無くすため自宅を買い戻す
次に家賃の負担を無くすために自宅を買い戻すことを提案しましたが、リースバック時に手に入った資金はすでに家賃の支払いや、生活費に充てており、手元の現金では不可能で、こちらも断念されました。 解決に向けた提案
本動画では、解決に向けた提案として、フラット35の親子リレー返済型を活用した買戻しについて紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。 SBIシニアの住まいとお金に相談
SBIシニアの住まいとお金では、リースバックのお悩みを住宅ローンのプロに直接相談できます。相談料等は全て無料です。セミナーや相談事例に関する質問や相談も受け付けています。ぜひお気軽にご相談ください。 60歳からのリースバック相談はこちら
この動画はこのようなお悩みをお持ちの方におすすめです
・住宅ローンのボーナス払いが厳しい方
・住宅ローンの返済額を減らしたい方 概要
SBIシニアの住まいとお金の住宅ローン相談に寄せられた実際のご相談を紹介します。今回の相談者は64歳の男性で、奥様と二人暮らしです。現在の住宅ローン残高は約1,600万円で、月々の返済額は11万円。毎月の支払は特段問題なく払えているようですが、年2回のボーナス返済額32万円の支払いがギリギリとのことです。来年に定年退職を迎えるため、今のうちに住宅ローンの返済額を減らせる方法は無いかと、ご相談を受けました。 ご相談者様の状況
・64歳男性
・住宅ローン残高 約1,600万円
・毎月の支払額 11万円
・ボーナス返済額 32万円(年2回) ご相談者のお悩み
・65歳の定年退職までにボーナス返済をなくしたい
・老朽化した自宅のリフォーム資金の借り入れもしたい アドバイス
ボーナス返済分を繰り上げ返済
まずは、ボーナス返済分の繰り上げ返済を提案しましたが、ボーナス返済分の残高が約400万近くあり、そこまでの預貯金を持たれていないとのことでしたので、断念されました。 他の金融機関で借り換え
次に他の金融機関での借り換えも提案しましたが、定年退職が迫っており、より良い条件での借り換えの審査が通りそうになく、こちらも断念されました。 解決に向けた提案
本動画では、リバースモーゲージ型住宅ローン「リ・バース60」を活用した住宅ローンの支払額の軽減方法を紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。 SBIシニアの住まいとお金に相談
SBIシニアの住まいとお金では、住宅ローンのお悩みを経験豊富な住宅ローンのプロに直接相談できます。相談料等は全て無料です。セミナーや相談事例に関する質問や相談も受け付けています。ぜひお気軽にご相談ください。 60歳からの住宅ローン相談はこちら