公開日:2025.10.15
住宅ローンを検討する際、「自分の年収でいくら借りられるのか」と気になる方は多いのではないでしょうか。この記事では、年収400万円〜1,800万円の世帯を対象に、住宅ローンの無理なく返済できる「借入適正額」の目安を早見表でわかりやすく紹介します。
また、将来の生活も見据えた住宅購入の注意点についても解説しています。年収別の詳細ページへのリンクも掲載しているので、ご自身の状況に合った情報をすぐに確認できます。
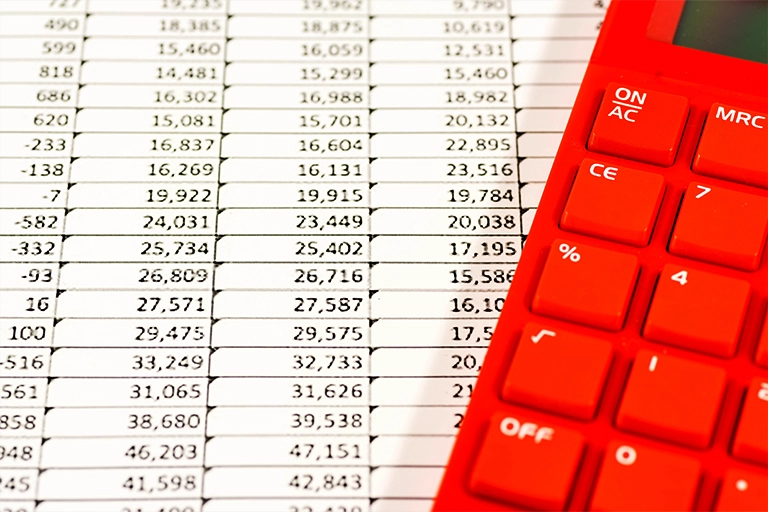
住宅ローンを検討する際、「いくら借りられるか」だけでなく、「無理なく返済できるか」も重要なポイントです。その判断には、以下の2つの指標が役立ちます。
年収倍率とは、住宅購入に必要な金額が世帯年収の何倍にあたるかを示す指標です。住宅金融支援機構の調査によると、フラット35利用者の年収倍率は、住宅の種類によって以下のように分布しています。
| 住宅の種類 | 年収倍率 |
|---|---|
| 土地付注文住宅 | 7.5倍 |
| マンション | 7.0倍 |
| 注文住宅 | 6.9倍 |
| 建売住宅 | 6.7倍 |
| 中古マンション | 5.5倍 |
| 中古戸建 | 5.3倍 |
出典)住宅金融支援機構「2024年度 フラット35利用者調査(年収倍率(融資区分別)の推移)p.12」
住宅金融支援機構の統計によれば、上図のように住宅の種類によって年収倍率は大きく異なります。ただし、この年収倍率は「購入可能な金額の目安」を示すものであり、必ずしも「無理なく返済できる金額」とは限りません。
また、今回のデータは住宅金融支援機構の調査結果に基づく【フラット35】に限ったものであるため、あくまで参考値として活用し、個別の資金計画を立てることが大切です。
総返済負担率とは、年収に対して、住宅ローンを含むすべての借り入れの年間返済額が占める割合です。この借り入れには、自動車ローンや教育ローンなども加味して計算されます。この総返済負担率は借り入れの際の審査基準にも利用され、住宅金融支援機構の「フラット35」では、以下のような基準が設けられています。
上記の数値はあくまで基準を満たすかどうかのラインで、「住宅ローン利用者調査(2025年4月)」によると、実際には「15%超~20%以内」の利用者が最も多く、全体の24.3%を占めています。
返済負担率が低いほど、教育費や老後資金など将来の支出にも余裕を持てます。「いくら借りられるか」ではなく「無理なく返済できる金額」を意識することが、後悔しない住宅購入につながります。
出典)住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査(返済負担率)p.7」
ここでは、総返済負担率20%を前提とした「借入適正額」を年収別に比較します。借入適正額は、以下の条件でシミュレーションしています。
| 年収 | 借入適正額 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 400万円 | 約2,361万円 | ー |
| 600万円 | 約3,542万円 | ー |
| 800万円 | 約4,723万円 | ー |
| 1,000万円 | 約5,904万円 | ー |
| 1,100万円 | 約6,494万円 | 詳細はこちら |
| 1,400万円 | 約8,265万円 | 詳細はこちら |
| 1,600万円 | 約9,446万円 | ー |
| 1,800万円 | 約10,627万円 | 詳細はこちら |
※【住宅保証機構株式会社】ローンシミュレーションをもとに筆者作成。
※詳細情報は順次公開予定です。公開後、リンクからご覧いただけます。
住宅ローンの返済だけでなく、購入後の生活も見据えた資金計画が大切です。ここでは、無理のない住宅購入を実現するために、特に重要な4つのポイントをご紹介します。
国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査」によると、住宅を初めて購入する方(一次取得者)の自己資金比率は、平均で20〜40%程度です。物件価格の2割以上の自己資金を準備できれば、借り入れを抑えられ、毎月の返済負担も軽減できます。
出典)国土交通省「令和5年度 住宅調査報告書(一次取得・二次取得別の購入資金)p.50」
近年、日銀の政策金利引き上げを受けて、住宅ローンで全期間固定金利を選ぶ人が増えています。2024年10月の調査では28.0%、2025年4月では30.7%と上昇傾向がみられます。一方、変動金利は借入時の金利が低く魅力的ですが、将来的な金利上昇によって返済額が増えるリスクもあります。
出典)住宅金融支援機構「住宅ローン利用予定者調査(2025年4月調査)p.15」
住宅ローン控除(住宅ローン減税ともいいます)とは、住宅ローンを利用して住宅の新築、取得または増改築等をした場合に利用できる、所得税額等を控除する制度です。住宅ローン控除を利用する場合、自身の状況に合わせてどういった条件でどのような控除が受けられるかを把握しておくことが大切です。
また、夫婦ともに安定した収入がある場合は、ペアローンを利用することで、借入可能額が増えるだけでなく、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるメリットもあります。控除額が増えることで、実質的な返済負担を軽減できる可能性があります。
ただし、諸費用が2本分かかる点や、離婚・収入変動などのリスクもあるため、慎重な検討が必要です。
住宅購入には、物件価格以外にも多くの費用がかかります。仲介手数料、登記費用、火災・地震保険料、固定資産税、修繕費など、維持費や初期費用も見逃せません。住宅ローン契約前に、諸費用の総額をしっかり把握しておきましょう。
住宅ローンは、単に「いくら借りられるか」ではなく、「無理なく返済できるか」を基準に考えることが大切です。年収倍率や総返済負担率といった指標を参考にしながら、将来のライフイベントや収入の変化も見据えた資金計画を立てましょう。
特に、総返済負担率を20%以内に抑えることで、教育費や老後資金など、将来の家計への影響を抑えることができます。また、自己資金の準備、金利タイプの選択、住宅ローン控除の活用、諸費用の把握など、購入前に確認すべきポイントも多岐にわたります。
「この金額なら無理なく返済できる」と思えるラインを見極めることが、後悔しない住宅購入への第一歩です。
執筆者紹介
次に読むべき記事
「5,000万円の家を買いたいけれど、自分の年収で本当に買えるのか」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか。 この記事では、フラット35を利用して5,000万円の家を購入する際の金利...