更新日: / 公開日:2025.11.27
こんにちは、公認会計士の千日太郎です。前回の記事(【フラット35】11月金利は1.90%に決定|千日太郎の予測と機構債分析!)では、【フラット35】の11月金利を1.89%~1.92%と予想し、結果は1.90%となりました。予測は的中しましたが、その背景には国債利回りや機構債の動き、そして住宅金融支援機構の「激変緩和」策がありました。
今回は、2025年12月の【フラット35】金利を予想します。11月20日に発表された機構債の表面利率は2.30%と大幅に上昇し、新発10年国債利回りも1.79%まで急伸。さらに、逆ザヤ問題が過去最大に拡大する中、住宅金融支援機構がどこまで金利を抑えられるのかが焦点です。
この記事では、12月の金利予想レンジと2つのシナリオ、その背景にある国債利回り・機構債・ローンチスプレッド・E55債の影響をわかりやすく解説します。
2025年12月の【フラット35】金利は1.97% に決定しました(更新日:2025年12月1日)。
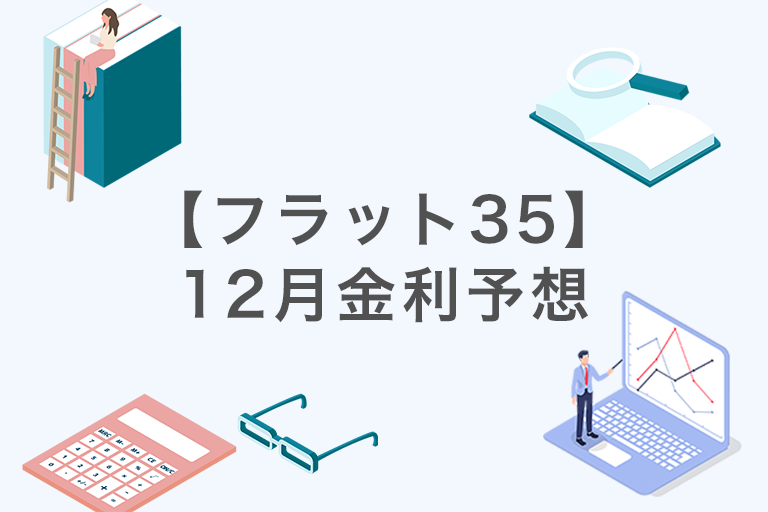
2025年11月の【フラット35】金利は1.90%に決定しました。これは、前回の記事で提示した予想レンジ(1.89%~1.92%)の下限に収まる結果です。
予想が的中した背景には、国債利回りや機構債の動き、そして住宅金融支援機構による「激変緩和」策がありました。急激な金利変動を避けるため、機構は過去の事例同様、上昇幅を最小限に抑える調整を行ったと考えられます。
【フラット35】の金利は、以下の簡易式で説明できます。
2025年10月の主要データは以下のとおりです。
このデータから、機構債の表面利率は前月比で0.03ポイント上昇していますが、【フラット35】の10月から11月にかけての金利は、住宅金融支援機構が調整幅を広げることで、0.01ポイントの上昇で抑えられました。これは、住宅ローン利用者の負担増を避けるための政策的判断といえます。
最大の理由は、住宅金融支援機構が逆ザヤを許容して低金利を維持していることです。
逆ザヤとは、機構債の「仕入れ金利」が【フラット35】の「貸出金利」を上回る状態を指します。
2025年10月の機構債の表面利率が2.15%に対し、2025年11月の【フラット35】は1.90%。その差は0.25ポイントで、過去最大の逆ザヤ幅となっています。営利を目的としない住宅金融支援機構だからこそ可能な調整ですが、この状態が長期化すれば、今後の金利政策に影響を与える可能性があります。
逆ザヤの推移(機構債 vs フラット35)
| 月 | 機構債表面利率(機構債発表日) | フラット35金利 | 金利差(逆ザヤ) |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 1.94%(5月22日) | 1.89% | -0.05ポイント |
| 2025年7月 | 1.88%(6月20日) | 1.84% | -0.04ポイント |
| 2025年8月 | 2.02%(7月18日) | 1.87% | -0.15ポイント |
| 2025年9月 | 2.08%(8月21日) | 1.89% | -0.19ポイント |
| 2025年10月 | 2.12%(9月19日) | 1.89% | -0.23ポイント |
| 2025年11月 | 2.15%(10月17日) | 1.90% | -0.25ポイント |
※出典)住宅金融支援機構「既発債情報」
2025年11月は、新発10年国債利回りが1.79%まで急上昇し、機構債の表面利率も2.30%と過去半年で最大の上昇幅を記録しました。
通常であれば、この水準の機構債利率に連動して【フラット35】の金利も大きく上昇するはずですが、住宅金融支援機構は過去の傾向から急激な変化を避ける調整を行うと見られます。
そのため、2025年12月の【フラット35】金利は1.90%~1.95%と予想します。これは、前月比で最大でも+0.05ポイント程度の上昇にとどまる見込みです。
【フラット35】金利推移と2025年12月予想
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月千日太郎の予想 | |
|---|---|---|---|---|
| 【フラット35】の金利(※) | 1.89% | 1.89% | 1.90% | 1.90%~1.95% ※12/1発表の金利は1.97%でした |
※出典)住宅金融支援機構【フラット35】「借入金利の推移(借入期間21年以上35年以下、融資率9割以下、新機構団信付きの場合)」
このシナリオでは、住宅金融支援機構が国債利回りや機構債の急騰をあえて反映させず、金利を据え置く、または最小限の上昇に抑えると想定します。
背景には、住宅ローン利用者の負担増を避ける政策的意図があります。過去の事例でも、急騰局面では「激変緩和」が適用され、金利上昇幅は0.00~0.03ポイント程度に抑えられたケースが多く見られます。この場合、2025年12月の金利は前月と同じ1.90%となる可能性があります。
もう一つのシナリオは、逆ザヤの限度を考慮しつつ、過去の調整パターンを踏まえたものです。2025年10月の機構債の表面利率と2025年11月の【フラット35】の金利差は0.25ポイントと過去最大に拡大しました。
もしこの差を維持するなら、2025年12月の【フラット35】金利は2.05%になる計算ですが、これは前月比で+0.15ポイントと急激な上昇です。過去の事例では、こうした急騰局面では「激変緩和」により上昇幅を0.05ポイント程度に抑える傾向があるため、1.95%が現実的な上限と考えられます。
主要データ(2025年11月20日時点)
| 機構債発表日 | 2025年8月21日 | 2025年9月19日 | 2025年10月17日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|---|---|
| 機構債の表面利率(※1) | 2.08% | 2.12% | 2.15% | 2.30% |
| 新発10年国債利回り(※2) | 1.61% | 1.61% | 1.64% | 1.79% |
| ローンチスプレッド(※1) | 47bps(0.47%) | 51bps(0.51%) | 51bps(0.51%) | 51bps(0.51%) |
※1 出典)住宅金融支援機構「既発債情報」
※2 10年国債利回りは便宜上、機構債表面利率からローンチスプレッドを差し引いた率としています。
2025年10月から11月にかけて、新発10年国債利回りは1.64%から1.79%へ急伸しました。この背景には、高市政権による積極的な財政出動と、インフレ期待の高まりがあります。
特に、2025年度補正予算案の規模拡大が議論され、国債増発観測が強まったことで、長期金利に上昇圧力がかかりました。国債利回りは【フラット35】の金利決定に直結するため、この急騰は12月金利予想において最も重要な要素です。
機構債の表面利率は、2025年10月の2.15%から11月には2.30%へと0.15ポイント上昇しました。これに対して、【フラット35】の金利は10月から11月に1.90%へわずかに上昇しただけで、両者の差は0.25ポイントに拡大しました。
この「逆ザヤ」は過去最大であり、住宅金融支援機構が収益を犠牲にして低金利を維持している状態です。非営利の政策機関だからこそ可能な対応ですが、この状況が長期化すれば、今後の金利政策に影響を与える可能性があります。
ローンチスプレッドとは、機構債の表面利率と新発10年国債利回りの差であり、2025年12月時点で0.51%の横ばいです。この横ばい傾向は、機構債のリスクプレミアムが安定していることを示し、市場が長期金利の急騰を一時的な現象と見ている可能性を示唆します。
つまり、スプレッドが拡大していないことは、【フラット35】の金利が急騰するリスクをやや緩和する要因となっています。
2025年10月に導入されたE55債は、住宅金融支援機構が新たに採用した資金調達手段です。従来の機構債と同様、住宅ローン債権を裏付けに発行されますが、特徴はより低コストである点にあります。
具体的には、表面利率が1.63%と機構債よりも低く、ローンチスプレッドも0.36%と小さいため、発行額が拡大すれば、機構はより安価に資金を調達でき、【フラット35】の低金利維持に寄与する可能性があります。今後、E55債の発行動向は、フラット35の金利動向を占う重要な指標となるでしょう。
E55債の概要
| 発表日 | 表面利率 | 10年国債利回り | ローンチスプレッド |
|---|---|---|---|
| 2025年10月22日 | 1.63% | 1.27% | 0.36% |
※1 出典)住宅金融支援機構「貸付債権担保E55債発行条件」
2025年12月の【フラット35】金利は、前月比で最大+0.05ポイント程度の上昇が見込まれます。仮に金利が1.90%から1.95%に上昇した場合、借入金額3,000万円・返済期間35年のケースでは、月々の返済額が764円増加します。
一見すると小幅な増加ですが、長期的には総返済額で約320,000円の差が生じるため、金利動向を注視することが重要です。
今後の金利上昇局面では、以下のポイントを押さえておく必要があります。
特に、今後の国債利回りの動向次第では、民間銀行の固定金利が先に上昇する可能性があるため、早めの行動がリスク回避につながります。
高市政権の積極財政とインフレ圧力により、長期金利は上昇傾向にあります。しかし、住宅金融支援機構は政策的役割を担う非営利機関であり、「住宅金融の円滑化」を目的に、急激な金利上昇を抑える調整を続けています。
さらに、2025年10月に導入されたE55債による低コスト資金調達が進めば、【フラット35】の低金利維持に寄与する可能性があります。ただし、逆ザヤが長期化すれば、将来的には金利引き上げ圧力が強まるため、2026年以降は緩やかな上昇トレンドに入る可能性も視野に入れておくべきでしょう。
執筆者紹介